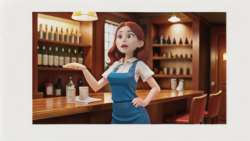日本酒
日本酒 お酒造りの計測器:浮ひょう
浮き秤とは、液体の重さ比べをするための道具です。重さ比べとは、あるものの重さと、基準となるものの重さを比べた値のことです。普通は、液体の場合は、基準となるものとして4度の水を使います。浮き秤は、アルキメデスの法則に基づいて作られています。アルキメデスの法則とは、水などの液体に物を入れると、その物は、押しのけた液体の重さに等しい浮く力を受けるというものです。言い換えると、液体の重さ比べが大きいほど、浮き秤はより浮きやすく、重さ比べが小さいほど、浮き秤はより沈みます。この法則を使って、浮き秤の沈み具合から液体の重さ比べを読み取ることができます。浮き秤は、ガラスで作られた管のような形の道具で、下の部分にはおもりが入っています。このおもりによって、浮き秤はいつもまっすぐ立って液体に浮かびます。そして、管の上の部分には目盛りが刻まれており、液体の表面と目盛りの交わる所から重さ比べを読み取ることができるのです。例えば、水の重さ比べを測る場合、浮き秤は目盛り1の所に来ます。もし、測る液体が水より重い場合、浮き秤は1よりも上の目盛りに来ますし、軽い場合は1よりも下の目盛りに来ます。浮き秤には様々な種類があり、測りたい液体の重さ比べの範囲によって使い分けられます。例えば、牛乳の重さ比べを測るための牛乳用浮き秤や、お酒の重さ比べを測るための酒用浮き秤などがあります。また、目盛りの刻まれ方も様々で、重さ比べを直接読み取れるものや、ボーメ度や比重などの別の単位で目盛りが刻まれているものもあります。そのため、使用する際には、どの種類の浮き秤を使うべきか、目盛りはどのように読み取れば良いのかをしっかりと確認することが大切です。