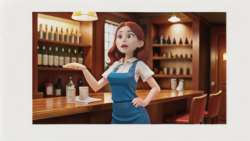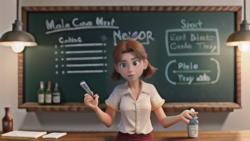日本酒
日本酒 醪管理の要、BMD値とは?
酒造りは、蒸した米に麹と水を混ぜ合わせ、発酵させることでお酒を生み出す、繊細な技の結晶です。この発酵過程で生まれる、お酒の素となる液状のものを「醪(もろみ)」といいます。醪の良し悪しはお酒の質に直結するため、醪の状態管理は酒造りの肝となります。醪の管理には、温度や湿度、そして発酵の進行具合を細かく観察し、調整することが求められます。その中でも、発酵の進み具合を数値で表す指標として「BMD値」があります。このBMD値は、醪の糖度とアルコール度数の変化を捉えることで、発酵の状態を正確に把握するのに役立ちます。BMD値は、ボーメ度(ボーメ)と呼ばれる比重計を用いて測定します。ボーメ度は液体の比重を表す単位であり、この値の変化から醪中の糖分がアルコールへと変化していく様子を推測できます。発酵の初期段階では、醪にはたくさんの糖分が含まれています。酵母はこの糖分を分解し、アルコールと炭酸ガスを生成します。そのため、発酵が進むにつれて糖分は減少し、アルコール度数は上昇していきます。この糖分の減少は醪の比重を軽くし、ボーメ度の低下として観察されます。つまり、BMD値の変化を追うことで、発酵の進行状況をリアルタイムで把握できるのです。BMD値は、酒造りの工程管理に欠かせないツールとなっています。毎日、同じ時刻にBMD値を測定し記録することで、発酵のスピードや傾向を掴むことができます。このデータに基づいて、温度調整や仕込みのタイミングなどを微調整することで、目指すお酒の味わいを作り出すことが可能になります。また、過去のデータと比較することで、発酵の異常を早期に発見し、品質の低下を防ぐことにも繋がります。BMD値は、経験と勘に頼っていた酒造りを、より科学的で確実なものへと進化させる、重要な指標と言えるでしょう。