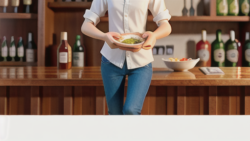日本酒
日本酒 米の粒の重さとおいしさの関係
米の良し悪しを見分ける上で、お米一粒一粒の大きさや重さは大切な手がかりとなります。その中でも「千粒重」は、お米の品質を見極める上で欠かせない尺度です。千粒重とは、その名の通り、千粒のお米の重さを指します。この数値によって、お米の粒の大きさや充実度を正確に知ることができます。一般的に、千粒重が重いお米ほど、粒が大きく、しっかりとした歯ごたえがあります。炊いたときも、粒が立ってふっくらと仕上がります。反対に千粒重が軽いお米は、粒が小さく、軽い食感になりがちです。そのため、粘り気が少なく、さっぱりとした味わいを求める方に向いています。この千粒重は、新しい品種の開発や田んぼでの管理においても、重要な基準となっています。農家の方々は、丹精込めて育てたお米の千粒重を測ることで、より美味しいお米を作ろうと日々努力を重ねています。お米の種類によって千粒重は異なり、例えば普段私たちがよく口にするうるち米は、およそ20から28グラム程度です。もち米は、うるち米より少し軽く、およそ18から25グラム程度です。私たちが普段お米を選ぶ際にも、この千粒重に目を向けてみると、より自分の好みに合ったお米を見つけやすくなります。粒が大きく、しっかりとした食感のお米が好みの方は、千粒重が重いお米を選びましょう。反対に、軽い食感のお米が好みの方は、千粒重が軽いお米を選ぶと良いでしょう。普段何気なく手に取っているお米ですが、千粒重を知ることで、お米選びがより楽しく、そして奥深いものになるでしょう。