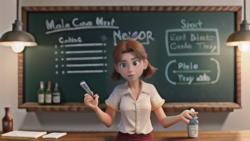その他
その他 水質の鍵、生化学的酸素要求量
生化学的酸素要求量(略してビーオーディー)は、水質の汚れ具合を調べる大切な目安の一つです。水の中に溶けている生き物の栄養となる物質が、目に見えない小さな生き物によって分解される時に、どれだけの酸素が使われるかを数値で表したものです。この数値が高いほど、水の中の汚れが多く、水質が悪いと判断できます。水の中には様々な生き物が住んでいますが、目に見えない小さな生き物たちは、生き物の栄養となる物質を分解することで生きています。この分解の過程で、水に溶けている酸素を使います。この小さな生き物たちを微生物と呼び、栄養となる物質を有機物と呼びます。微生物は有機物を食べて、水と二酸化炭素に分解しますが、この時に酸素を必要とします。ビーオーディーの値は、水の中にどれだけ有機物が溶けているかを示す指標となります。有機物が多いということは、微生物が分解するのに多くの酸素を必要とするため、ビーオーディーの値が高くなります。逆に、きれいな水には有機物が少ないため、ビーオーディーの値は低くなります。私たちの生活から出る排水、例えば台所やお風呂、トイレからの排水、そして工場からの排水には、多くの有機物が含まれています。これらの排水が川や湖に流れ込むと、水中の有機物の量が増え、ビーオーディーの値が上昇します。ビーオーディーが高い状態が続くと、水中の酸素が不足し、魚や水草などの生き物が生きていけなくなります。そのため、川や湖などの水質を守るためには、ビーオーディーの値を常に監視し、適切な対策を講じる必要があります。ビーオーディーは、私たちの水環境を守る上で、非常に重要な指標なのです。