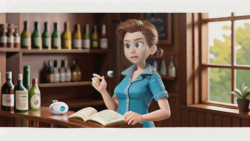 日本酒
日本酒 お酒本来の味わいを楽しむ!素濾過の魅力
お酒を選ぶ時、ラベルに「素濾過(おりがらみ)」と書かれたものを見かけることがあります。なんとなく耳にしたことはあっても、どんなお酒なのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。今回は、日本酒本来の味わいを大切にした「素濾過」という製法について、じっくりと解説していきます。日本酒は、もろみを搾った後、貯蔵し、瓶詰めする前に濾過という工程を行います。これは、お酒の濁りをなくし、味を安定させるために行われる大切な作業です。濾過には主に「活性炭濾過」と「精密濾過」の二種類があり、多くの日本酒はこれら二つの濾過を両方行います。活性炭濾過では、活性炭を用いることで、お酒の色や香りを調整し、すっきりとした味わいに仕上げます。精密濾過は、細かい目のフィルターで濾すことで、より透明なお酒にします。しかし、これらの濾過を行うと、日本酒本来の風味や香りが損なわれてしまうこともあります。そこで、日本酒本来の味わいを最大限に楽しみたいという声に応えて生まれたのが「素濾過」です。素濾過とは、活性炭濾過をせずに、精密濾過だけを行う、あるいは濾過を全く行わない製法のことです。活性炭濾過をしないことで、日本酒本来の豊かな風味や香りがそのまま瓶の中に閉じ込められます。素濾過のお酒は、濾過を最小限に抑えているため、にごりがあり、独特の風味と力強い味わいがあります。フレッシュな果実のような香り、濃厚な米の旨味、そしてほのかな甘みが複雑に絡み合い、他のお酒では味わえない奥深さを楽しむことができます。また、蔵によっては、あえて濾過を全く行わない「無濾過」という製法を用いる場合もあります。無濾過のお酒は、より一層濃厚な味わいと、もろみ由来の複雑な香りが特徴です。日本酒造りの奥深さを知ると、お酒選びがもっと楽しくなります。いつものお酒とは少し違った、個性豊かな「素濾過」のお酒を、ぜひ一度お試しください。







