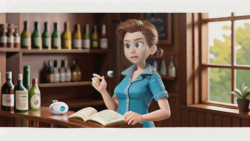日本酒
日本酒 深く味わう濁り酒の世界
濁り酒とは、日本酒の種類の中でも、独特の白濁色が特徴のお酒です。お酒のもととなる、醪(もろみ)を布で濾す工程で、あえて目の粗い布を使うことで、醪の中に含まれるお米の粒や酵母などの成分がそのままお酒の中に残ります。この製法こそが、濁り酒の独特の風味を生み出す秘訣です。一般的な日本酒の場合、醪を搾った後に、細かい目のフィルターできれいな液体になるまで濾過を行います。しかし、濁り酒はこの細かい濾過の工程を省くか、あえて粗い目の布で濾すことで、醪の豊かな成分をそのまま残します。そのため、濁り酒には、お米の粒や酵母がそのまま含まれており、白く濁って見えるのです。この濁りこそが、濁り酒の最大の魅力です。口に含むと、とろりとした滑らかな舌触りと共に、お米本来の旨味とほのかな甘みが広がります。さらに、酵母が生きていることで、かすかな発泡感を感じることができ、フレッシュな味わいが楽しめます。まるで、発酵途中の醪をそのまま味わっているかのような感覚を体験できるお酒と言えるでしょう。濁り酒は、日本酒本来の風味をそのまま味わえるお酒として人気があります。濾過されていないからこそ味わえる、濃厚な風味や複雑な味わいは、日本酒好きにとってはたまらない魅力です。また、甘口のものが多いため、日本酒初心者にも飲みやすいお酒としておすすめです。冷やして飲むのはもちろん、温めて飲むのもおすすめです。温めることで、より一層甘みが増し、体の芯から温まることができます。