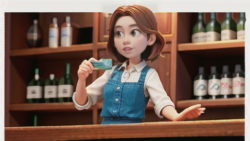日本酒
日本酒 日本酒のふるさと、御影郷を探る
兵庫県神戸市の灘区から東灘区にかけて広がる灘五郷は、日本を代表する日本酒の産地です。その中心に位置する御影郷は、現在の神戸市東灘区沿岸部の御影地区にあたります。古くから良質な水と米に恵まれたこの土地は、江戸時代後期から明治時代にかけて酒造りが大きく発展しました。灘五郷の中でも特に質の高い日本酒を生み出す地域として名を馳せ、現在もその伝統は脈々と受け継がれています。御影郷の日本酒の質の高さを支える要素の一つは、六甲山系の伏流水である「宮水」です。六甲山の花崗岩層によって長い年月をかけて濾過された宮水は、カルシウムとカリウムを豊富に含み、鉄分が少ないという特徴を持っています。この宮水は、酵母の活動を活発にし、雑菌の繁殖を抑えるため、きめ細かくすっきりとした味わいの日本酒を生み出すのに最適です。もう一つの重要な要素は、酒造りに最適な米、特に「山田錦」です。山田錦は、兵庫県で生まれた酒米の最高峰と称される品種です。大粒で心白が大きく、溶けやすい性質を持つため、良質な麹造りに適しています。御影郷では、この山田錦をはじめとする酒造好適米を厳選し、最高の日本酒造りに活かしています。そして、これらの恵まれた自然環境に加え、御影郷の蔵人たちは、長年培ってきた伝統の技を守り、丹精込めて日本酒を醸し続けています。それぞれの酒蔵が独自の製法を磨き上げ、洗練された香り高く味わい深い日本酒を生み出しています。宮水と山田錦、そして蔵人たちの技術が三位一体となって、御影郷の日本酒を唯一無二のものにしていると言えるでしょう。現在でも多くの酒蔵が軒を連ねる御影郷は、日本酒好きにとって聖地とも言える場所です。訪れる人々は、それぞれの酒蔵で個性豊かな日本酒を味わい、その奥深さを堪能することができます。