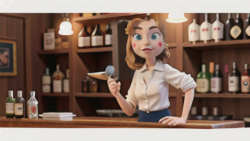スピリッツ
スピリッツ 無色と有色の蒸留酒
蒸留酒は、その色によって大きく二つの種類に分けられます。一つは、無色透明の蒸留酒で、ホワイトスピリッツと呼ばれています。もう一つは、琥珀色や茶褐色など様々な色合いを持つ蒸留酒で、ブラウンスピリッツと呼ばれています。この色の違いはどこから生まれるのでしょうか。蒸留酒の色は、樽熟成の有無によって決まります。ホワイトスピリッツは、樽で熟成させずに瓶詰めされます。そのため、蒸留したばかりの無色透明な状態を保っています。蒸留直後の風味をそのまま楽しめるのが特徴です。味わいは一般的にすっきりとして軽やかで、様々な飲み物と混ぜ合わせやすいことから、カクテルのベースとしてよく用いられます。例えば、ウォッカやジンなどがホワイトスピリッツに分類されます。ウォッカは穀物などを原料とし、無味無臭に近いことから、他の飲み物の風味を邪魔することなく、カクテルに奥行きを与えます。ジンは、大麦などを原料とし、蒸留の際にジュニパーベリーという香辛料を加えることで、独特の松のような香りを持ちます。この爽やかな香りが、ジントニックなどのカクテルに欠かせない要素となっています。一方、ブラウンスピリッツは、樽の中でじっくりと時間をかけて熟成されます。この熟成期間の長さによって、色が濃くなり、味わいに深みが増していきます。樽材に含まれる成分が、蒸留酒に溶け出すことで、淡い金色から深い褐色まで、様々な色合いが生まれます。また、樽材の種類によっても、バニラのような甘い香りやスモーキーな香りなど、様々な風味が加わります。ウイスキーやブランデーなどがブラウンスピリッツの代表です。ウイスキーは大麦などを原料とし、オーク樽で熟成させることで、芳醇な香りと深いコクが生まれます。ストレートやロックでじっくりと味わうことで、その複雑な風味を堪能できます。ブランデーは、果実酒を蒸留して作られ、オーク樽で熟成させることで、フルーティーな香りとまろやかな味わいが生まれます。食後酒として楽しまれることが多く、その優雅な香りは、特別な時間を演出してくれます。このように、蒸留酒の色は、その製造過程や風味を理解する上で重要な手がかりとなります。ホワイトスピリッツの持つすっきりとした軽やかさ、ブラウンスピリッツの持つ複雑な香りと深いコク。それぞれの個性を楽しみながら、蒸留酒の世界を探求してみてはいかがでしょうか。