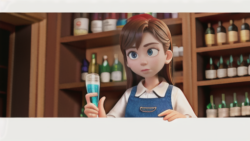日本酒
日本酒 酒造りの肝、打瀬工程とは?
お酒造りにおいて、酒母造りは大切な工程です。酒母とは、お酒のもととなるもので、その出来具合がお酒全体の味わいを左右します。酒母造りの中で、「打瀬(うたせ)」と呼ばれる工程があります。打瀬とは、蒸し米、麹、水を混ぜ合わせた酒母を、加熱する直前の期間に行う作業のことです。蒸し米、麹、水などを混ぜ合わせたばかりの酒母は、温度が上がりやすい状態にあります。この時、急激に温度が上がると、雑菌が繁殖しやすくなり、目指すお酒の味わいを損ねてしまう可能性があります。そこで、打瀬によってゆっくりと時間をかけて酒母を冷まし、雑菌の繁殖を抑えるのです。打瀬では、温度管理が特に重要になります。高い温度では雑菌が繁殖しやすく、低い温度では酵母の活動が弱まってしまいます。そのため、酵母が元気に育ち、雑菌の繁殖を抑えることができる、ちょうど良い温度を保つ必要があります。蔵人たちは、長年の経験と勘を頼りに、酒母の温度変化を注意深く見守りながら、細やかな温度調整を行います。打瀬によって丁寧に温度管理をすることで、酵母は健やかに増殖し、雑菌の繁殖を防ぎ、良質な酒母を得ることができます。良質な酒母は、その後の工程で腐敗や風味の劣化を防ぎ、目指すお酒の味わいに近づくための重要な鍵となります。まさに、打瀬は、美味しいお酒造りのための土台を作る、最初の関門と言えるでしょう。