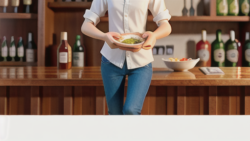日本酒
日本酒 おいしいご飯を炊くための替え水の役割
炊きたての、ふっくらとしたご飯は、日本の食卓にはなくてはならないものです。炊き方には様々なコツがありますが、見落とされがちなのが、お米を研ぐ際の水の扱いです。お米を研ぐ工程で水を入れ替える「替え水」は、昔から伝わる知恵であり、ご飯をおいしく炊くための大切な点です。お米の表面には糠や塵などの不純物が付着しています。これらの不純物は、ご飯に雑味や臭みを与え、炊き上がりの風味を損ねてしまう原因となります。そこで重要なのが、替え水による丁寧な研ぎです。最初の水は、お米の表面についた糠を洗い流すためのものです。濁った最初の水はすぐに捨て、新しい水で研ぎ始めます。研ぎ方は、力を入れすぎず、優しく丁寧に行うのがポイントです。力を入れすぎると、お米が割れてしまい、炊き上がりがべちゃっとした食感になってしまいます。お米を手のひらで優しく包み込むようにして、水を切る動作を繰り返します。水の色が透明に近づくまで、数回水を替えて研ぎましょう。目安としては、冬場は4~5回、夏場は6~7回程度です。夏場は水の温度が高いため、雑菌が繁殖しやすいため、冬場よりも多く水を替えることが推奨されます。また、水の温度にも気を配りましょう。冬場は冷たい水で研ぎ、夏場はぬるま湯を使用すると、お米の吸水が均一になり、炊き上がりがふっくらと仕上がります。水道水をそのまま使うと、カルキ臭さが残ってしまうこともあるため、浄水器を通した水を使うか、一度沸騰させた水を冷まして使うのも良いでしょう。替え水を適切に行うことで、ご飯の雑味や臭みが抑えられ、お米本来の甘みと旨味を存分に引き出すことができます。ぜひ、これらの点に注意して、おいしいご飯を炊いてみてください。