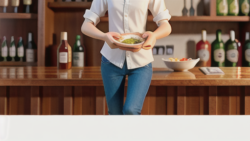 日本酒
日本酒 酒造りに欠かせない糠の役割
お酒造りに欠かせないお米を磨く工程で生まれるのが糠です。実はこの糠、精米の具合によって様々な種類に分けられます。まず、お米を少しだけ磨いた時に出るのが赤糠です。精米歩合で言うと九割くらいの時です。玄米の表面に近い部分なので、砕けたお米の粒や胚芽が多く含まれており、色が赤みを帯びているのが特徴です。赤糠は栄養が豊富なので、漬物に利用したり、肥料として使われたりしています。次に、精米歩合が八割五分くらいになると中糠が出てきます。赤糠に比べるとお米の粒は少なくなり、糠特有の成分が濃くなっています。中糠も赤糠と同様に、漬物に使われたり、畑の肥料として活用されたりしています。さらに磨きをかけて、精米歩合が七割五分くらいになると白糠になります。白糠は赤糠や中糠に比べて白っぽく、きめ細かいのが特徴です。ぬか床に使うと、まろやかで風味豊かな漬物を作ることができます。また、洗顔料として使うと、肌の汚れを優しく落としてくれます。そして、精米歩合が七割五分よりも進んでくると、特上糠または特白糠と呼ばれる糠になります。これはお米の中心部分に最も近い糠で、非常にきめ細かく、純白に近い色をしています。高級なぬか床の材料として使われたり、お菓子の材料として使われたりもします。このように、糠は精米の度合いによって見た目や性質が大きく変わり、用途も様々です。お酒造りだけでなく、私たちの生活の様々な場面で役立っているのです。


