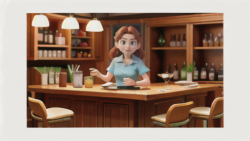日本酒
日本酒 酒造りの技:汲掛けとは
お酒造りにおいて欠かせない工程の一つに、酒母造りがあります。酒母とは、いわばお酒の母となるもので、最終的なお酒の味わいを左右する重要な役割を担っています。この酒母造りは、蒸した米、麹、水を混ぜ合わせるところから始まります。まず、蒸米は米を蒸したものですが、蒸し加減が重要です。蒸し加減が不十分だと、麹菌が米の中までしっかりと繁殖することができず、良い酒母ができません。逆に、蒸しすぎると米がべたついてしまい、これもまた酒母造りには適しません。次に麹ですが、これは蒸米に麹菌を繁殖させたものです。麹菌は米のデンプンを糖に変える役割を担っており、この糖が後に酵母によってアルコールへと変化していきます。そのため、質の良い麹を使うことが、美味しいお酒造りの第一歩と言えるでしょう。そして水ですが、これは酒造りにとって非常に大切な要素です。仕込み水と呼ばれるこの水は、酒の味を大きく左右します。硬水、軟水など水質によって、出来上がるお酒の風味も変わってくるのです。これらの材料を混ぜ合わせた後、タンクの中でじっくりと時間をかけて発酵させていきます。この過程で、乳酸菌や酵母といった微生物が活躍します。まず乳酸菌が働き、乳酸を生成することで雑菌の繁殖を抑えます。そして、その後、酵母が糖をアルコールへと変換していくのです。この酵母の働きが、お酒の風味を決定づける重要な要素となります。酒母造りは、これらの微生物の働きを巧みにコントロールする職人技の結晶です。温度管理や、櫂入れと呼ばれる撹拌作業など、職人の経験と勘が、美味しい酒母を生み出すのです。こうして丁寧に育てられた酒母は、やがて醪(もろみ)へと移され、次の工程へと進んでいきます。まさに、酒母造りは、お酒造りの根幹を成す重要な工程と言えるでしょう。