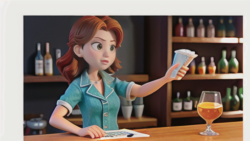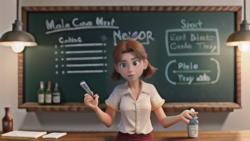日本酒
日本酒 増醸酒とは?日本酒造りの奥深さを探る
増醸酒とは、日本酒の一種で、お酒造りの過程でアルコールを加えることで、独特の風味と長持ちする性質を実現したお酒です。 これは、簡単に言うと、もととなるお酒にさらにアルコールを足して造るお酒のことです。増醸酒造りでよく用いられるのが、三倍増醸法と呼ばれる方法です。この方法は、通常の日本酒の造り方とほぼ同じように米、米麹、水を混ぜてお酒のもととなる醪(もろみ)を造ります。そして、この醪が完成に近づくタイミングで、醸造アルコールを加えます。 醸造アルコールとは、サトウキビなどを原料として作られた純度の高いアルコールのことです。これを加えることで、日本酒本来の風味はそのままに、アルコール度数を高め、お酒が腐敗するのを防ぐ効果があります。増醸酒のアルコール度数は、一般的に17度から22度程度と高く、しっかりとした深い味わいがあるのが特徴です。普通の日本酒に比べて、口に含んだ時にコクや力強さを感じられます。また、腐敗しにくいので、長期間の貯蔵にも向いています。貯蔵することで、味わいがまろやかになり、熟成による独特の風味の変化を楽しむこともできます。増醸酒の種類も近年では多様化しています。例えば、甘口で飲みやすいもの、辛口でキリッとしたもの、熟成によって琥珀色に変化し、深い香りを放つものなど様々です。このように様々な味わいの増醸酒が登場したことで、日本酒を好む人たちの間で、再び注目を集めています。増醸酒は、日本酒の伝統的な製法に工夫を加えることで生まれた、独特の魅力を持つお酒と言えるでしょう。その奥深い味わいと多様性を、ぜひ一度楽しんでみてはいかがでしょうか。