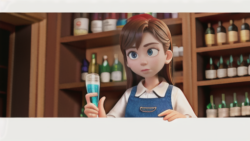ウィスキー
ウィスキー ウイスキーの香味を決定づける「前溜」とは
お酒作りにおいて、蒸留はなくてはならない工程です。お酒のもととなる発酵した液体を熱し、アルコールや香りの成分を気体にして、それを冷やして再び液体に戻す作業です。この一連の作業の中で、最初に出てくる液体が「前留」と呼ばれます。単式蒸留器、釜型の蒸留器から最初に流れ出るこの液体は、まさに蒸留の最初の恵みと言えるでしょう。ウイスキーの特徴となる様々な成分が含まれていますが、同時に好ましくない香りや味の成分も多く含まれているため、製品化されるウイスキーには使われません。このため、後から出てくる「中留」と分けて集められます。蒸留が始まった直後は、沸点が低い成分から順番に気体になっていきます。前留には、ツンとした刺激臭や不快な風味を持つ成分が多く含まれています。例えば、アセトアルデヒドや酢酸エチルなどです。これらの成分はウイスキーの香りを悪くするだけでなく、人体にも悪影響を与える可能性があるため、しっかりと取り除く必要があります。蒸留作業のまさに最初の難関であり、職人の技術と経験が試される工程と言えるでしょう。前留を適切に処理することは、質の高いウイスキーを作る上で欠かせない要素です。前留の成分と量は、発酵の進み具合や蒸留器の形状、加熱方法など、様々な要因に影響されます。そのため、蒸留の担当者は、五感を研ぎ澄まし、常に状態を確認しながら作業を進める必要があります。前留と中留を正確に見分けるには、長年の経験と高度な技術が求められます。こうして丁寧に前留を取り除くことで、雑味のない純粋なウイスキーの香味を守ることができるのです。まさに、最初の恵みである前留を適切に処理することで、その後の工程で得られる中留の品質が決まり、最終的に美味しいウイスキーが出来上がるのです。